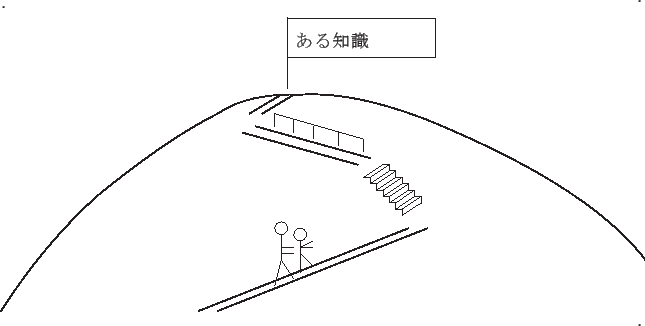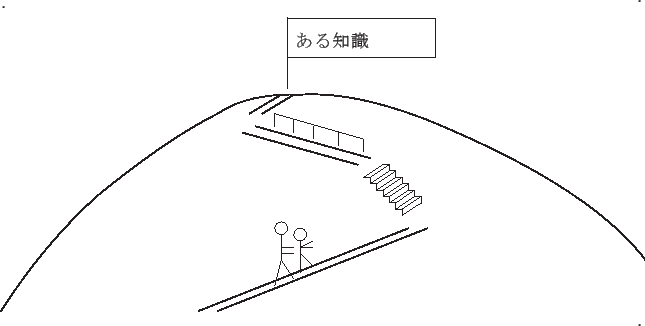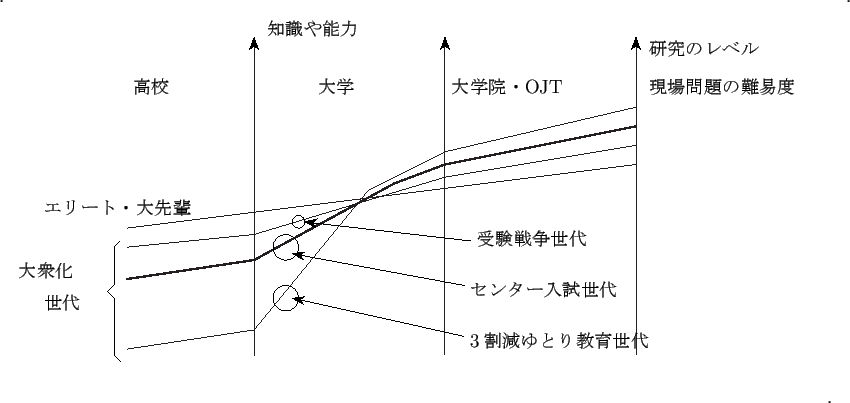高校までは,既にわかっていることを学ぶ,というより覚える。
大学以降に利用できる道具を頭の中に組み込むことが目的の
教育である。
もちろん,すべての人間がすべてを理解できるはずはない。
だから目標は高くしておいて最低限その目標の50%, 60%を
会得することが義務教育の目的ではなかったのか。
その最低限にも達成できない,いわゆる「落ちこぼれ」は昔から
いたはずだが,そこは丁寧な指導で卒業はできていたと予想する。
ところが,落ちこぼれを落ちこぼれとしてしか扱えない
低級な教諭が増えたことや,親のしつけが行き届かず社会生活が
できない子供が増えたこと等から問題が発生して,
「ゆとり」といった言葉が出てきたのではないだろうか。
実は大学においても落第ギリギリの人間をうまく卒業させてきたように
感じる。第1著者はかつて,
そういった学生に対して厳しい対応を要求したことがあったが,
先輩教官から丁寧な説明を受けて,
そういったうまく卒業させることも
容認できるようになった。
学生本人が大人でありさえすれば,いろいろな対処の仕方はある。
さて,高校までの教育の特徴を挙げてみよう。
- 既にわかっていることを習う。
- 丁寧なガイドがある。
- 教諭は背中を押してくれる。
- ゴールを身に付けるのが目的。
- 記憶と反復学習に努める。
となるのではないだろうか。
これに対し,大学・大学院における教育の特徴は
次のようになると思う。
- わかっていないこと【を解く・に対処する】方法を学ぶ。
- 教員は自分がベストだと思う方法で知恵を与えてくれるだけだ。
- 学生自らが,自らの理解できる言葉で解釈し
模索する必要があることから,復習が一番大事である。
- いろいろなプロセス(調査・検討・開発・解決:アカデミック・スキルと
呼ぶらしい)を身に付けるのも目的であるが,
免許や資格を取得することは目的ではない。
学んで情報を身に付けるのは学生自身であるから,
教員が教えた通りに,教えた言葉で身に付ける必要は全く無い。
自分がいつでも使える情報にしたいならば,自分の言葉に翻訳し直す
必要がある。
面白い例を書いておこう。
例えば大学入試の物理学の力学の問題を理学部と工学部の
先生に解いてもらおう。
ある先生は「多分,こういうプロセスを使えば解ける」と述べて筆は動かない。
ある先生は,30分以上時間をかけて(受験生は20分くらいで解く)「微分
方程式を使ってもいいなら,これが答」と出してくる。
一方受験生の答案の採点現場では,答は合っている答案に書いてある
解き方を理解するまでに,数人の先生が30分以上も悩むこともある。
つまり,高校までの教育と大学における教育・研究とにおいて,
頭(道具)の使い方にはほぼ全く共通点は無いと考えないといけない。
以前は親が,大学のこういった教育体制や,大学生は大人として
扱われることが,しつけとして家庭で教育されていたが,
昨今はそうではないらしく,大学における勉強に対する考え方が間違っている上に,
子供じみた権利だけを主張する学生が増えてしまっていると感じる。
さて,時代の変遷と大学教育の難度の増加について,
わかり易い模式図を元工学部長の四ッ柳隆夫先生
が描いてくださったが,
それをかなり簡略化して,かつ少し誇張して描いたのが次の図である。
学部における専門科目の講義内容そのものも昔に比べて
増えたこともあるが,3年生の夏学期までの勉強がとても重要で,かつ
辛くなってきている。
それに伴い,昔のいわゆる教養教育が縮小され,また
エリート・大先輩が学部で習った専門科目の中にはもはや大学院でも
開講されていない部分も生じている。
これが望ましい形とは思えないが,必要なことを最小限教授するという
観点からの設定になってしまっているのが現実だ。
教員が教えた通りに身に付ける必要は無いと書いた。
それは,問題に対峙したときにすぐに取り出せる「活かせる知」に
しておくためには,自分の言葉に翻訳して身に付ける必要があるからだ。
では,その使える知を活かして考えて問題を解決するということは
どういうことだろう。
京谷孝史先生が卒業式の祝辞で使う論語の言葉
「子曰 学而不思則罔 思而不学則殆」は次のような意味と捉えてもいい。
「学んで身に付けても考【わ|え】ずに使【わ|え】ないなら意味が無い。
考えるだけで学ぼうとしなければ何も解決できない。」
考える・知識を使うとはどういう行為だろう。
英語に`serendipity'という単語がある。ある辞典には,
「思わぬ発見をする才能」「運よく発見したもの」等とある1が,そうじゃない。
- 寝ても覚めても考え続けること
- 試行錯誤をし続けること
で得るかもしれない発見とその能力が`serendipity'であるとされている。
無駄が多いが,それ無しには絶対に現れない機会,
現れるとも限らない機会のことである。Pasteurの`Chance favors the prepared mind.'とほぼ同じだと思う。
普段から身の回りの現象に関心を持ってそれを自分の知識で
解釈する努力を続けておくことが望ましいし,一旦
問題を抱えてしまったら,頭の中の道具を駆使して延々と試行錯誤を
続ける必要があるということである。
最終的にはその問題は解決できないかもしれないが,
それも何らかの足しになるのだ。
卒業論文の課題解決あたりから始まって就職して仕事をしている間は,
この「考え続ける」という行為が必要になるのだ。
また教員との関係についていい言葉「師を見るな、師が見ているものを見よ」を
見つけたが,出典は不明。
高校までの「基礎」とは応用が利くものではなく,ものごとを科学的に
考察するための道具である。
これに対し,大学で教育している『基礎』とは,今すぐ使える技術を
教える代わりに
将来の解決すべき難問にチャレンジするための応用可能な道具である。
文献著者である鈴木基行先生は,構造設計に
当たっては手間やお金がそれほどは必要無いくらいの「ちょっとした
工夫」を加えるだけで,設計荷重を超えるような外乱に対する事故を
避ける可能性を増やすことができるとおっしゃっている。
つまり,そういうことができるように大学では『基礎』を教えているのである。
そしてそれは時々刻々とアップデートされるため,
講義中に板書すらされずに言葉で伝達されることも多い。
教科書を読めば単位がもらえると思っている学生は,
その考えを早く改めるべきだろう。
朝日新聞(2006/3/20)の特集「大学」から適当(いい加減という意味;
以下あちこちに著者加筆有)に引用しておこう。
企業は即戦力は期待していない。
「すぐに役立つ(だけの)人はすぐに役立たなくなる人である。」は
戦前の東京大学の谷村豊太郎先生の言葉である。
それよりも,大学で得た知識を自分の言葉に翻訳したデータベースとして持ち,
それを用いていろいろ想像(simulation)して新しい提案ができる能力が
期待されている。
さてその特集では,企業が求めるものについて
経団連教育問題委員会 宇佐美聡企画部会長
(三菱電機常任顧問)は
- 志と心:
- 倫理観と責任感。
規範の中で使命感を持って取り組む姿勢。
- 行動力:
- 実行力とコミュニケーション能力。
情報収集とその利用によって目標を達成する。
- 知力:
- 基礎学力+(結果的に)独創性。
深く考え抜く力。「使える知」。
だと述べている。加えて
- 相手の意見を聞いた上で自分の意思を伝える力。
- 自分の言葉で自分の考えを伝えられる人材。
も重要だ。さらに,次のようなことが読み取れる。
- ○○大卒だから・・・ということは全くあり得ない。
- コミュニケーション能力とは英語ができることだけじゃない!
(大学教員も勘違いしてませんかぁ)
- 就職してから「自分に合わない」は,どの職場も駄目ってこと。
最近ミシェラン・ガイドに掲載された寿司店の小野二郎氏は
「自分を仕事に合わせる」べし(NHK教育TV 2008/1/8)と述べている。
- 「工学系だから人文・社会系はまるで駄目」は論外。
- 小さくまとまって面白みに欠ける学生は欲しくない。
- きれいな受け答えができるだけの馬鹿は要らない。
- 自分の言葉に翻訳して勉強しデータベース化する。
復習して基礎をしっかり身に付ける。折に触れて勉強をする。
学んだことを友人に教えてみてごらん・・・
- 勉強を効率化しない。たいていは自己満足の手抜き。
これができるのは秀才だけ。
- 友人をたくさん作る。視野を拡げる。
いろいろな価値観が存在することを知る。本を読む。
- 大人と会話をする。社会の常識を身に付ける。
- 自分の考えを持つ。自分の頭を使う。使える知識にする。
- 約束を守ること。決まり(暗黙のも含む)を守ること。
残念ながら著者も実行できていないことだが。
あの某細胞研究のゴタゴタの際,実験ノートの作り方についてマスコミでも
何度も発信されたが,解析的であろうと数値的であろうと,
あるモデルに基づく理論的研究(非実験的研究)の場合の研究ノートの
作り方も同じである。
- 最初のページ欄外に日付を書き順に
ページ番号を振る。綴じてないレポート用紙でよく,表にしか記載をしない。
裏は軽微な追加事項等を日付入りで書き込むために使う。
- 途中(例えばp.5とp.6の間)に追加挿入する場合には
その日付を記し,誤解を生まない
ようなページ番号(例えばp.5a, 5b...)を振る。
- 鉛筆書きでいいが消しゴムは不可。間違い箇所やページにはボールペンで
赤
 印をつけ,
うまくいかなかった箇所も同様にした上で理由を朱書きする。
印をつけ,
うまくいかなかった箇所も同様にした上で理由を朱書きする。
- 指導教員の打ち合わせメモ等も日付を付した上で,適所に挟んでおく。
- ある程度の結果が出た段階毎に順番に
表紙付きのフォルダに左2穴で綴じる。
- これでは計算間違いの振りをした捏造は避けられないが,
式展開の途中が少しでも消されていたら信頼性は無いと判断すべきだ。
ただし数値計算結果の真偽の判断は非常に難しい。
さて,文献で内田樹先生がおっしゃっていることを
つまみ食いしておきたい。ここも
一部分の抽出なので誤解を生む可能性は高いが,インパクトを与える
ためにも敢えて一部分を引用しておく。
真意を知るには文献を読んでいただきたい。
それは文部科学省の杉野剛さんとの2回の対談の節(原文縦書き)である。
- 大学教育のアウトカムとは何ぞやについて‘数値的には表示しにくいもの’と
した上で‘資格や免状や、TOEICのスコアというのは、その副産物で’あると
する。本来の大学の教育目的は‘「成熟した市民を育てるため」’である
と断言する。
- 大学には‘俗世間とは違う空間があって、
そこは外とは違う時間が流れており、違う度量衡が機能している’とする。
そして‘そういう非-社会的な空間、外の社会との温度差が
ある場所が若い人たちを健全に育ててゆくためには絶対に必要だと’考えている。
さらに‘社会の価値観としっかり一線を画すということに大学の責務がある。’と
断言している。
- 学ぶというところに‘対価と商品の等価交換という発想で
学校にやってくる人たち’はそぐわない。学ぶことはできないとする。
‘「学ぶ」というのは努力と成果の等価交換ではない’と断言している。
どうだろう。どういう風に読者は感じますか。
昨今の某大学教員も
かなり勘違いして教育をしていないか,というのも
正直な感想である。
Iwakuma Tetsuo
Tue, 14 Oct 2025 13:20:08 +0900
: Stardate [-25]1225.90